あなたの暮らしを豊かにするYouTube紹介ブログ。
女性落語家古今亭佑輔さんの「祐チャンネル」(後編)
このチャンネルは、落語家の古今亭佑輔さんが江戸の食文化を紹介するチャンネルです。
さっそくチャンネル内を拝見
チャンネル登録者数 623 動画総数 9本 (2022年9月24日登録)
5本目 爆食い 江戸時代の大きなお寿司!?その実態を調査してきました。!お店の人の神対応に感激!
(1分27秒)茂八寿司 (千葉県館山市)にて、田舎寿司を注文。江戸時代から受け継がれるこの店定番のメニューです。「メッチャ大きい!」手で食べることにしましたが、手のひらの半分お寿司で埋まってしまいました。
江戸時代の人はこんなに大きな寿司を食べていたのです。ほとんどおにぎりサイズ。ご飯だけで何グラムあるんでしょう?
(4分30秒)鯵の姿寿司 頭が落とされないでそのまま付いています。
「お寿司はおやつだった」らしいですね。元々お酢が無かった時代はお米で発酵させていたそう。鮒寿司がお寿司の原型でお酢が使われるようになって、発酵させる手間がなくなりました。外で、仕事の合間にサッと食べられるように握り寿司ができたのだとか。
ネタも今とは全然違ったそう。鉄火巻きは鉄火場っていう博打をする場所で片手でつまめるようにとできたらしい。(諸説あり)サンドイッチと一緒。
(7分10秒)
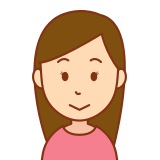
噺家って食べる時結構人に合わせる。一緒に食べる人が早食いなら早く食べるし、ゆっくりなら遅く食べるし。先輩を待たせちゃいけない。早く食べ過ぎてプレッシャーを与えちゃいけない
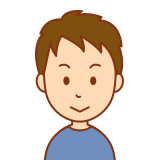
お寿司握ってみますか?
鯵の姿寿司を握らせてくれる。 三日かけてお酢につけるそう。
シャリが大きいのが特徴。手のひらで転がしているうちに形になっていく。握った時にぎゅうぎゅうにしない。フワッと握る。ご飯が多そうに見えるんだけど空気が入っているのでそんなでもない。鯵のネタを乗っける。
卵焼き 卵何個分?というほどの大きさ。(見た目3個分はありそう)
(14分30秒)
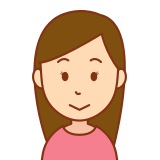
江戸前のお寿司が大きかったのと、何か関係があるのですか?
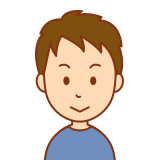
推測ですが閉鎖的な地形で、文化の発展が止まっていて、昔は汽船が出ていたんですよ。築地までだと陸路だとすごく時間がかかるんですけど、水路の方が早いので鮮度を保つために味を船で運んでいた。それで、江戸時代のお寿司の文化がそのまま残ったのではないでしょうか。
残った酢飯はいくら丼に。お土産用に入れ物に入れて持ち帰ります。
視聴後の感想
祐さんは噺家さんなんですよね。美しすぎる!噺家にしておくには勿体無い(失礼!)いや、これからはジェンダーフリーの時代。男の世界、女の世界はないのです。ぜひ活躍していって欲しい。
それにしても、江戸時代の人はたくさん食べたのですね。こんなに大きいお寿司がおやつだと言うのだから驚きです。きっとそれだけ体も動かしたのでしょうね。
ところで、身長高いですね。
動画を見て知ったのですが、さすがにミスコンで優勝しただけの方であります。背が高い!
調べてみましたら身長163センチ。
ついでに言うと、B85 W64 H87!まあ!
7本目 超絶品 江戸庶民の味「ねぎま鍋」を堪能! 特別ゲスト歌舞伎脚本家の戸部和久さん登場!!
「江戸が食べたい」をテーマに語ります。戸部和久さんのお宅を訪問。なんと純和風の素敵なお宅。憧れますね。
縁側に座り、火鉢で鉄瓶にお湯を入れ酒を沸かす。凄いなあ。これ、いつもやっているのかなあ。さすが歌舞伎の脚本家だ。日常生活から江戸の文化の中にいるんだなあ。
「ねぎま」を食することに。まずは熱燗で乾杯。美人はなんでも似合います。
(3分09秒)
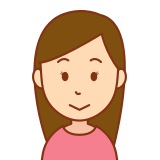
戸部さんにとっての食道楽って何ですか?
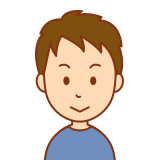
お酒が好きなのでお酒に合うもの。そして旬を感じたい。その時に一番エネルギーの強いものを食べる。免疫力も上がりますし、美味しいし。美味しいってものは食べ物にエネルギーが満ちている。
ねぎま鍋を作ります。
火鉢に鉄鍋をのせるという江戸庶民がやってたであろう方法で調理します。
ネギを焼くところからスタート。
(4分52秒)
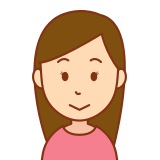
歌舞伎の脚本家というのはどういうお仕事なんですか。
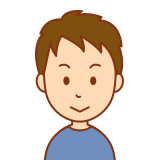
古典をやっているのでそういうお仕事は、無いんじゃないですか、とよく言われます。しかし、歌舞伎も現代に生きている芸能、芸術です。
今活躍している役者さんに合わせて古典の作品にアレンジしたり、全く新しい作品を作るので、脚本のお仕事はあリます。
歌舞伎の台本は基本的にあてがきで作られております。昔の江戸時代の人の為にあてがきにされたものを今の人たちがやるのです。
今の人たちと時間軸が違いますね。昔だったら日が暮れて夜になったら真っ暗になってしまう。昔は歩くしか無かったのが今は移動時間が速い。
昔のままやっていたら、長いとか、くどいとかになってしまうので、役者さんのそれぞれに合わせて書き換えていくという作業をしています。
割り下を投入(割り下とはだし汁に醤油味醂砂糖などの調味料を加えて煮立てたおもに鍋物や丼物に使用される調味料のこと。)
マグロを投入、レアぐらいがいいんだそう。
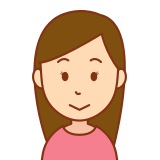
庶民の味なんて嘘みたい。
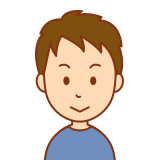
ねぎまを知っているのと知らないのとでは、作品の見方が変わってきますね。
視聴後の感想
動画の中で戸部さんも仰っていたんですが、ねぎまっていう、こんなに美味しい食べ物を江戸時代の人はみんな食べていた。だからねぎまを題材にした作品が大衆にわかって貰えた。
それと同じで、昔のものの良さを分かって欲しいと思う。歌舞伎にしても、落語にしても。

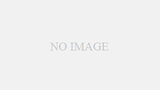
コメント