あなたの暮らしを豊かにするYouTube紹介ブログ
今回紹介するのは、「チームみらい応援チャンネル」
このチャンネルは、チームみらいと安野貴博さんを応援する動画を投稿。2025年8月13日に登録したばかりのチャンネルです。
2025年度の参議院選挙において100万票以上を集め目標だった国政政党化を果たしたチームみらい。
そんな国政政党のチームみらい代表、安野たかひろさんの今後の言動を紹介することで、視聴者の皆さんと共に日本の未来について考えていこうという狙いで作られました。
私たちの所得が倍増する未来、子育て先進国な未来、公平な税・社会保障制度を再構築する未来。
そんな未来を、チームみらいは叶えてくれると思っています。
- 安野たかひろ マニフェストはAIが主役
- 中国のdeepseakAIが尖閣諸島を中国領土と答えるなど、AIの学習データにバイアスがあり、世論戦や歴史戦に利用される不安がある。 この対策はどうすべきか。
- 日本のデジタル教育は遅れ、2030年に79万人のIT人材不足が予想される。AI産業発展のため子ども・一般・職業訓練でどんな教育振興が必要か。
- AI推進法で作る基本計画にどんな理念を入れるべきか?人間中心のAI社会を目指すために一番大切考え方は何か?
- AIのリスク最小化に加えてビジネス機会創出が大切。安野さんのいう「日本にAI勝機がある」理由をお聞かせください。
- 安野さんが述べた「プロンプトの指示出しが重要でこれによってAIが大きく活用できる」という点について詳しくお聞かせください。
- 海外の20代30代がAI革新を担う一方、日本は能力があるのに人材が育たない。スキルが正当に評価される環境づくりの方法をお聞かせください
- 都知事選でAI活用し15万票獲得したが、政治でのAI利用は不正やデジタル格差の懸念もある。政治とAIの関係をどう考えますか。
- AIが偽情報・誤情報の作成拡散に使われ情報操作のリスクが高まっている。この問題への技術対策とルール整備について教えてください
- 政治の世界はAIに最も縁遠く経験や勘を重視する業界だと思う。このような政治業界でのAI活用についてどうお考えですか
安野たかひろ マニフェストはAIが主役
デジタル大臣か適任すぎる・・・AI法案に対する質疑応答(2025年4月16日衆議院内閣委員会)
2025年8月17日投稿 要点整理
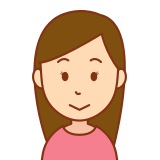
今回は安野さんが国会でAIについて答弁をした映像を文字起こしして要点をまとめました。参議院選挙に立候補する前のことです。
しかし、その頃からデジタル大臣にふさわしいオーラが全開!
質問に関する的確な回答をご覧ください。
中国のdeepseakAIが尖閣諸島を中国領土と答えるなど、AIの学習データにバイアスがあり、世論戦や歴史戦に利用される不安がある。 この対策はどうすべきか。
LLM(大規模言語モデル)というのは認知線との相性というのは非常に良い。悪い意味で良いと思っている。そういった懸念というのは充分にありうると思う。
1つ目の解決策としては国産のLLMを我が国でも作っていくということ。
2つ目は、このAIによる認知戦というのは技術で対抗して行く。人力でやるというのはなかなか難しい領域。そういった意味で本法案はAIの利活用しっかり進めていくという意味では意義があると考えている。
日本のデジタル教育は遅れ、2030年に79万人のIT人材不足が予想される。AI産業発展のため子ども・一般・職業訓練でどんな教育振興が必要か。
重要だと考えているのはAIへの広いアクセスを担保することだと思う。
中高生向けの教育プログラムに参加して中高生見ているが、非常に今の中高生プログラミングを学ぶスピードは速い。我々の時代よりも圧倒的に速い。チャットGPTやLLMにいろいろ聞きながらどんどん自分で学び続けている。
同じ中高生であっても、親からチャットGPTだとかLLMのアクセスを渡されていない学生と渡されている学生では大きな差がついてしまっている。この労働のアクセスっていうのを担保するっていうのが一つ重要なのではないかなと考えている。
AI推進法で作る基本計画にどんな理念を入れるべきか?人間中心のAI社会を目指すために一番大切考え方は何か?
一人一人の可能性を広げるというところかなと思っている。
同じテクノロジーでも人間の可能性を狭めるような使いかたもできるし、広げるような使い方もできる。このAIという技術我々の人間の可能性を広げていくという方向に使っていくことが重要だと思う。
AIのリスク最小化に加えてビジネス機会創出が大切。安野さんのいう「日本にAI勝機がある」理由をお聞かせください。
簡単な話でないが、しっかりと今の段階から取り組んでいくことで勝機あるのではないかと思っている。
その背景には二つ理由がある。
一つはこういった新しい技術が広がっていくときには、その業界で既に勝っていた勝者と敗者が入れ代わりやすいタイミングができる。
例えばインターネットやSNSが出てきたことによって、Google Facebookなどの企業はビッグテックとしてどんどん大きくなったタイミングがあった。
スマートphoneが出てきたときにも、Apple、サムスンのようなスマートphoneの企業というのがどんどん大きくなっていった。
今回はAI。全く新しいパラダイムの技術が出てきたこのタイミングは、今まで負けていた会社やなかった会社が上に上がっていく、非常にあの稀有なチャンスだと思う。
そういった基盤モデルを活用しながら事業をする、AIを使いこなすレースっていうのはまだまだ始まったばかり。ここはまだ無数にチャンスがあると思っている。
2つ目の理由としては日本のその人口構成がもたらすインセンティブというところ。労働人口というのがどんどん日本はこの先減っていく。そうなると雇用の問題よりもこの減っていく人不足の状況をどう解消するのかということで、各社AIを積極的に導入するインセンティブというのが生まれている。
この勢いをうまく活用して、この始まったばかりのレースでしっかり勝っていくのが重要というのが私の意見。
安野さんが述べた「プロンプトの指示出しが重要でこれによってAIが大きく活用できる」という点について詳しくお聞かせください。
プロンプトエンジニアリングについては、さまざまな現状テクニックが存在する。
最近私が見て一番驚いたのは、深呼吸をしろっていうのをAIに言うと、AIはもちろん肺はないわけですけれども、なぜか精度が上がる。こういう細かいテクニックっていうのはたくさんある。
こういう細かいテクニックを一般の利用者が全部知らないといけないわけではない。細かいテクニックがなくても同じように精度が出せるように、各社頑張っておられる。一般消費者として普通に使うユーザーとして、そこまで意識しなくても良くなる未来っていうのが来そうだなと思っている。
そうなっていくとやはり必要な情報を的確に与えるという意味で、対人間と接しているような形で部下のマネジメントと同じような機能っていうのが求められていくのかなと思っている。
海外の20代30代がAI革新を担う一方、日本は能力があるのに人材が育たない。スキルが正当に評価される環境づくりの方法をお聞かせください
まさにおっしゃるとうり。20代のような若い人材をいかに活用できるかっていうのがものすごく重要。
私もオープンAIの中の話やGoogleの中の話あるいはエックスAIの話聞くが、今の基盤モデルが強い会社は、主力の戦力が20代の前半の方がたくさんいらっしゃる。そういった若い方の力っていうのをフルに活用するのを各社やられているなと。
18歳時点でおそらく日本の理数系の学生の能力が非常に高い。このポテンシャルをうまく産業界スタートアップ業界でいかしきれないっていうのが一つの課題と思っている。
都知事選でAI活用し15万票獲得したが、政治でのAI利用は不正やデジタル格差の懸念もある。政治とAIの関係をどう考えますか。
こういったAI技術というのはどちらの可能性もある。つまり声を多く広く拾うために使うこともできれば、フェイクニュース、ディープフェイクのような問題を引き起こす可能性もある。
7月の都知事選挙ではブロードリスニングという言葉を使って説明たが、これブロードキャストの逆です。通常選挙ですと政治家候補者の考えている事を一方的にブロードキャストするというやり方がとられているが、今AIを活用することが出来ればいろんな人がいろんなことを言ってることを、ブロードリスニングできるんじゃないかと。
われわれはラグと呼ばれる仕組みを用いて、わたくしのマニフェストを学習させたAIを用意して、そこに24時間ずっと誰でも1対1で質問ができるようにした。こうすることによって二ついいことがあった。
1つ目は、どういった方がどういう質問を抱えているのか、どういう批判があるのかっていうことに対して、一人ひとりの聞き方を知りたいところに直接答えてくれるようになった。
2つ目は、その会話のログを見たときに、実はこの政策って全然響いてなかったとかここは実はものすごい批判が多いところなんだなって言うことを、学びを得られるということ。
こういうふうにAIを使ってコミュニケーション増幅して行くことで、よりいろんな方の声を聞くことができるのではないか。その活用というのはこれからの政治にとって重要なのではないかというふうに思っている。
AIが偽情報・誤情報の作成拡散に使われ情報操作のリスクが高まっている。この問題への技術対策とルール整備について教えてください
まだ触れられないところで二点だけ補足。
課題の一つは、このエスエヌエス上で生まれている誤情報名誉毀損みたいな情報が生まれる速度と、それを司法そういった処理をする速度にものすごく大きな差が開いてしまっている。
今後よりAIによって、この生まれる速度が加速して行く。処理する速度をどういうふうにあげていけるのか、そこが一つの課題になると思っている。
2つ目は、こういった誤情報の拡散をより止める一つの手段として、プリバンキングと呼ばれているような手段がある。これは誤情報が広まる前に、誤情報が現れる可能性があるということを周知するような手法。
もちろんこれですべて止めることはできないが、たとえば政治家の顔がディープフェイクで変えられてそれによって本当はやってないんだけどこういうこと言ってるっていうことが起きうるというのを、重要な政治的なイベントの事前にある程度周知しておくといったやり方は、一定有効だと研究でも示されている。
そういったものを取り込むというのは一つあるかなと思っております
政治の世界はAIに最も縁遠く経験や勘を重視する業界だと思う。このような政治業界でのAI活用についてどうお考えですか
個人的な感想と致しましては、道具としての使いどころというのはものすごくたくさんあると思っている。
勘と経験の意思決定というより、各国の過去の事例や科学的な事例をもとに、どう考えればよいのかと。AIのサポートできる部分っていうのはかなり沢山あるんだと言うふうに思っている。
そういう観点で最近いろんな政治家の方とお話させていただく機会多いが、政治家の議員の方のデジタルリテラシーというのは、もう少し高まるといいんじゃないかなというふうに思っている。ありがとうございます。
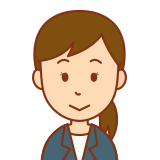
議論されていたAI推進法は、今年5月に成立したAIを研究し社会に広く生かして行くための日本初の法律です。
国としてAIを育てていこうという姿勢は、安野さんの話していた「人の可能性を広げるAI」や「子どもたちに平等なアクセスを」と言う視点もその理念に重なっていました。一方で、映像の中でも出てきたように、海外製AIの偏った回答や偽情報の拡散といった課題は、まだ十分な対策が盛り込まれていません。教育格差や政治におけるAI利用のルール作りもこれからの大きな宿題です。これからも安野さんとチームみらいを応援していきます!

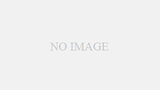
コメント